東京での生活では車やバイクを使う機会が少なく、運転免許証を更新せずに失効してしまいました。失効後2年ほど放置していましたが、子供ができると車移動のほう便利なケースも多いため、三鷹の運転免許試験場で「一発試験」に挑戦することにしました。
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!一発試験とは?
教習所に通わず、運転免許試験場で直接筆記試験と実技試験を受けて免許を取得する方法です。学科試験・技能試験ともに一発で受かる人は少なく、複数回挑戦するのが普通です。
鳥取県の場合は中部の運転免許試験場で一発試験を受験可能ですが、当時は東京都三鷹市に住んでいたため、府中運転免許試験場にて受験しました。そのほか鮫洲にもあります。
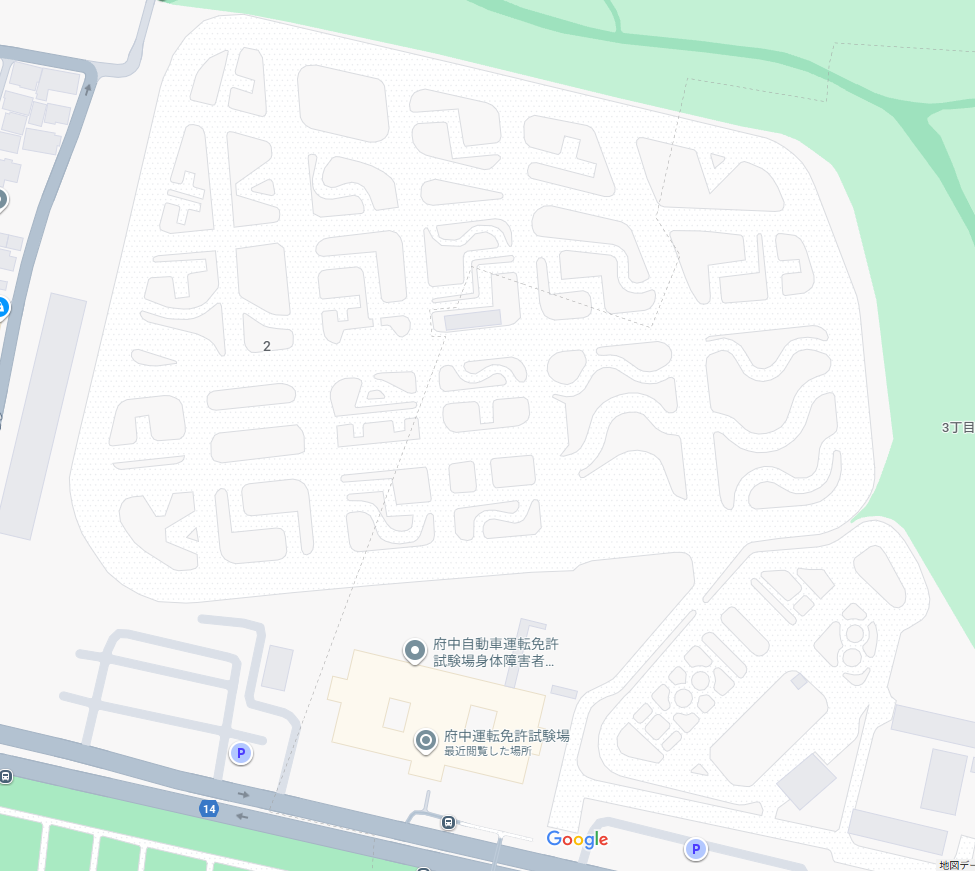
どちらも警察官が試験しますので、難易度は特に変わりないものと推測していますが、試験管による差異はあると感じます。
試験の流れと結果
結論としては、筆記試験はどちらも1発合格、技能試験はいずれも2回目で合格しました。
受験者は試験車両に乗り込む前の待機所で会話することが多いのですが、何回目の受験か皆さんが会話します。
多い方では6回目の人もいましたし、一度も免許を取ったことがないけど試験場開放日に練習してきた車好きの大学生もおられました。
試験場開放についても後述しますが、試験場開放で練習してきたからと言って1回目で合格している人は非常に稀(いないのではないか)と思われます。
- 仮免学科試験:1回目で合格
- 仮免技能試験:2回目で合格(受験6名、当日の合格者は私1人)
- 本免学科試験:1回目で合格
- 本免技能試験:2回目で合格(受験7名、当日の合格者は私1人)
試験費用の目安
一発試験は教習所より費用は安いですが、複数回受けると積み重なります。私の場合、合計で約2万5千円ほどかかりました。
それでも教習所に通うより遥かに安価ですし、短期間での取得ができました。有給を使って試験に落ちた日のラーメンは味がしませんでしたが良い思い出です。
- 受験手数料(学科・技能)… 2,550円/回
- 車両使用料(技能試験時)… 1,450円/回
- 仮免交付手数料… 1,150円
- 免許交付手数料… 2,050円
- 写真代… 750円(試験場内)
※合格するまでの回数分、受験料と車両使用料がかかります。
また現金や電子マネーの支払いにも対応していますので、この辺りも便利になりました。
試験予約と待ち時間
三鷹試験場(鮫洲でも同じと聞きますが)では技能試験の予約が混み合っており、毎回2週間~1か月先まで予約が埋まっていました。
また、試験予約は基本的に試験場の機械で予約操作が必要です。当日に電話して空きが出ている場合は飛び込みも可能なようですが、少ないようですので上記のような時間を要します。
私の場合、仕事の都合があり、どちらも1か月後に予約しました。2週間後でも空いてる日がありましたが、会議都合などにより断念。早ければ2か月とかからず取得可能と考えます。
筆記試験のポイント
ひたすらに過去問を解いてください。Webの問題集もありますし、過去問集を購入して解くのも良いです。
私の場合は過去問集を2冊購入し、何度やっても間違えない状態にしました。これは運ではなく勉強した量に比例しますので、しっかり勉強してください。
実技試験のポイント(一番重要)
この記事を読んでいる方が一番気になるポイントかと思いますので詳細に解説します。
試験管は助手席と後部座席に座り、違反の有無や試験の減点項目を確認します。減点項目により、違反切符を切られることはありませんでしたが、運転には細心の注意を払いましょう。
試験を受ける前提
まず一発試験を受けるにあたり、以下は必須条件です。
- 車の運転操作に不安がない
- 運転技術に不安がない
- 道路交通法を感覚ではなく、ルールとして理解している
私はMT車で受験しました。エンジンのかけ方、ミラーの調整、シートベルトをする、ウィンカーを操作する、ミッションのギアを操作する、安全確認の目視、このような操作はできて当たり前です。
バックギアの入れ方は車両によって異なりますが、試験管が優しかったのか試験開始前に全員の前で説明していました。
車も多種多様ですので、私は説明がなければバックギアに入れれなかったと思います。。
仮免技能試験
まず試験コースを覚える必要はありません。
試験官が適切なタイミングで指示します。指示されたら直後にウィンカーを出して目視確認、進路変更すれば、減点されている様子はありませんでした。
以下に注意点を記載します。
- 乗車前の安全確認(灯火類の点灯確認は不要)
- 発進前の安全確認(ミラー・目視)が徹底されているか
- 速度調整と進路変更時の合図のタイミング
- 目視確認の確実な実施
- 制限速度に合わせて走る
- S字・クランクは落ち着いて低速で
- 踏切通過や坂道発進の安定感
- 障害物横を通過する際の距離
- 右左折時や試験終了時の幅寄せ
試験場内は試験車両しかいないため、対向車や右左折時に臨機応変な対応が求められることはありません。上記を確実に実施すれば合格できます。
何より言っておきたいのは、教習所で習ったことを恥ずかしがらずに「ルール」と認識して着実に実施することです。
乗車前の安全確認なんかは1回目の試験でやってる人がいませんでしたが、2回目では、前の方が実践されていたのを見て思い出し、同じように実施しました。
私が1回目の落ちた理由は試験管のフィードバックで以下でした。
- ギアをしっかり変えて走ろうね
→場内は2速でも十分走れる速度でしたが、3速や4速まで使ってね、ということでした。 - 右左折後のハンドル操作がセルフステア(勝手に戻る現象)に任せてるね
→セルフステアに任せたハンドル操作なので、自分でハンドルを戻してね、と言われました。 - 信号で止まる場合など、クラッチを切った惰性走行をしているね
→普段だとよくやってしまうのですが、エンジンブレーキを使った減速をするため、クラッチを切ってブレーキで減速すると減点されます。 - 止まった時にクラッチに足を置いたままだね
→これも癖ですが、クラッチに足を置くと車両側にダメージがあります。遊びがあるので、即座に影響するわけではないですが、試験ではこちらもNGです。
試験官は目視と、センターコンソールあたりについているLEDランプでクラッチ操作を判断しており、クラッチに足を置いてると足が当たってチカチカ点滅するので気づくようです。 - 坂道発進で少し下がったね
→これは減点されると認識していましたが、体感でも下がったのを感じました。下がらないよう練習しましょう。
上記を2回目では着実にこなしたところ、合格時のフィードバックで特に気になるところはなかったと言われました。
これを言われないと合格するのはまず無理でしょうか。10回やっても合格できない人は、変わらないと思います。
本免技能試験
試験は実際の道路に出ますが、試験の開始場所までは試験管が運転します。この際には試験管の模擬運転と心得て、良く見ておきましょう。試験官の運転を真似すれば合格できます。
こちらも以下に注意点を記載します。
- 道路標識の順守
→制限速度、信号機の順守は絶対です。速度超過すると時間ごとに減点されます。信号の黄色侵入も絶対ダメです。歩行者用信号の点滅を確認したら、ブレーキに足を切り替えましょう。 - 右左折時の寄せと減速タイミング
→仮免と同じですが、試験管が道路案内します。この際に指示されたら直ぐにウィンカー操作、目視で安全確認右左折方向に幅寄せしましょう。まだもう少し先だからなーと思ってると試験管から2度目の指示があり、何か書いてる音が聞こえたので減点されていたと思います。 - 歩行者妨害、横断歩道の対応順守
→横断歩道での対応は普段やっていない方が多いと思うので要注意です。歩行者妨害しないことは当たり前として、横断歩道の手前では安全が確保できない場合に、一時停止して安全を確認してから発信することができます。怠ると減点です。 - ゼブラ(導流帯)に侵入しない
→信号で右折する際に、導流帯に侵入すると減点あるいは一発アウトです。普段は普通に走ることがあると思いますし、警察も意図的に取り締まることはないですが、正確にはアウト。 - 縦列駐車か切り返しは焦らずゆっくりやってOK
→制限時間はありません。侵入して切り返して出る。切り返し回数が増えると減点されるようですが、ポールに当たると一発アウトですので、無理せず切り返して出ましょう。
私の場合は1回目の試験で側道にゴミ収集車が止まっており、避けようと中央線側に寄ったところ、対向車が回避行動をとったとして、ブレーキを踏まれたうえ試験終了を宣言されました。
その前に導流帯に入っていたこともあるとは思いますが、減点合計が不合格に達したのか、終わりました。
上記以外は速度超過くらいでしたので、次回で合格すると思い2回目を受験して合格しました。1回目で指摘されたことは必ず順守する。これは絶対です。
運転免許試験場のコース開放
試験場はコース開放され、練習できるタイミングがります。大学生や主婦など時間に余裕のある方は、事前に練習するのをお勧めします。どこに障害物があるのかなど事前に学習できます。
一発試験のメリット・デメリット
メリット
- 何より教習所に通うより費用が安い
- 何より教習所よりは早く取得が可能(どこの教習所も混んでいる)
- 自分のペースで試験を受けられる
デメリット
- 試験の予約が取りにくく、間隔が空く
- 試験の合格基準が本当に厳しく、慣れていないと落ちやすい
- 実技練習を別途自費で行う必要がある場合あり
まとめ
三鷹の運転免許試験場での一発試験は、計4回の技能・学科試験を経て免許を再取得できました。
費用は抑えられる一方、予約待ちや試験の厳しさから時間と根気が必要です。これから挑戦する方は、事前に試験コースの傾向を把握し、練習場で技能を磨いてから臨むことをおすすめします。
おまけ
当方はそもそも運転技術も道路交通法も詳しいと自負しており、ウィンカー操作と右左折時のタイミングや一時停止などは、普段から当たり前にやっています。
そのおかげか2回で合格しましたが、試験管は2回目なの!?早いね。といった感じでした。
試験に落ちた日も合格した日も、合格者は私1人でしたので、狭き門であることは容易に想像できます。また、試験に合格させる必要がない試験場は、いとも簡単に不合格を宣言しますし、試験のための車両使用料も請求できます。
このことからも、一発試験で合格するには、当たり前を当たり前に実施できる知識と運転技術が必要です。自身のある方は是非お試しください。
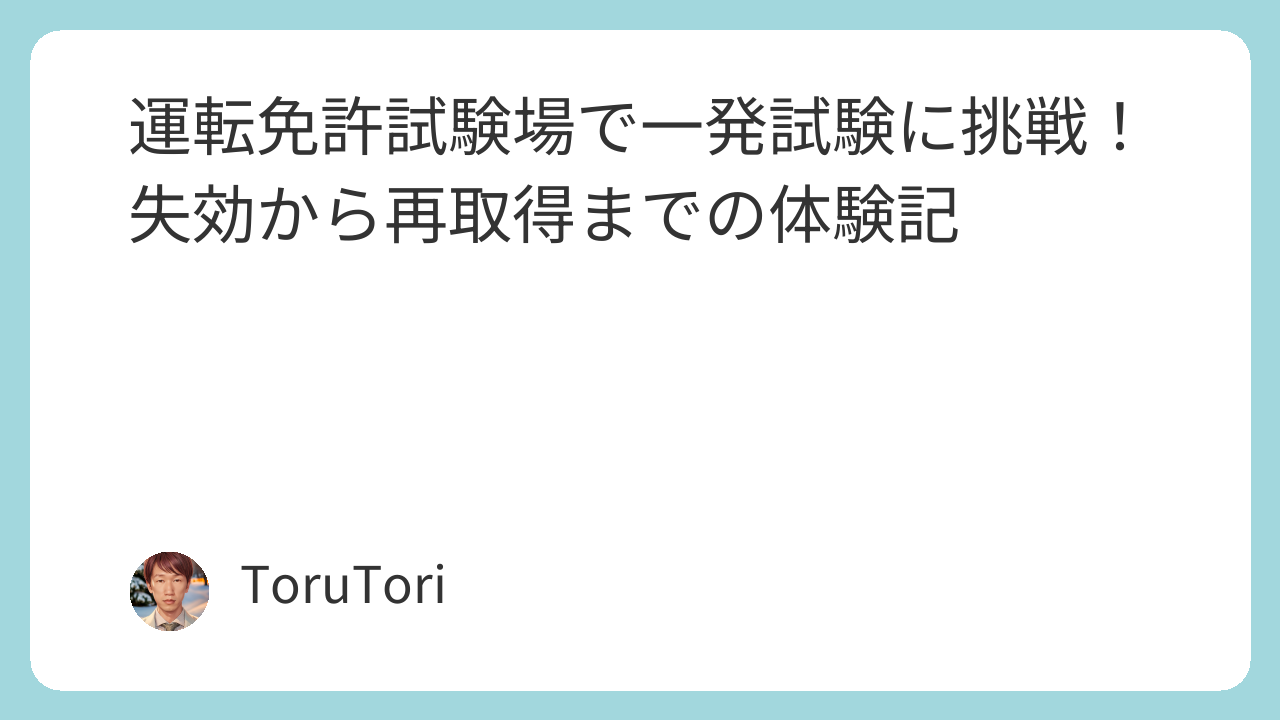


コメント