長年使用してきたデジタル一眼レフEOS 60D(2014年購入)から、ついにEOS R7に買い替えました。APS-Cセンサー搭載のEOSとしては初のミラーレスRシリーズであるR7は、モータースポーツなど動きの速い被写体を撮影してきた筆者にとって、大きな期待を抱かせるカメラです。この記事では、EOS R7をじっくり使い込んで見えてきた魅力と気になる点を、EOS 60Dとの比較を交えながら初心者~ミドルユーザー目線で徹底レビューします。
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!EOS R7のカメラ概要とアップグレードの背景
EOS R7は2022年に登場した、キヤノン初のAPS-CミラーレスRシリーズ機です。
有効約3250万画素のCMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xを搭載し、同時発表の入門機R10より上位に位置付けられるハイアマチュア向けモデルとなっています。
従来、一眼レフのEOS 7Dシリーズが担っていた高速連写・高速AFの系譜を継ぐモデルであり、動きものの撮影を得意とするとされています。
筆者はEOS 60Dを約10年間使用し、子どもやペット、さらにはサーキットでのレース撮影(モータースポーツ)なども楽しんできました。60Dは発売が2010年と少々古く、動体撮影性能に限界を感じていたこともあり、後継の90Dを飛ばしてこのR7へのステップアップを決断しました。
結果から言えば、EOS R7への乗り換えによって撮影体験は一変しました。後述するように、オートフォーカス性能や連写速度、画質などあらゆる面で60Dから大幅に進化しており、「すべてが進化した理想のステップアップ機」と言っても過言ではありません。では具体的にどのような点が進歩し、どんなメリット・デメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
開封時の簡易レビューはこちら
EOS R7のボディ・デザインと操作性
Canon EOS R7の本体前面。EOS 60Dよりコンパクトながら深いグリップでしっかりと握れる。
まず手に取って感じるのは、ボディのサイズ・重量の違いです。EOS R7本体(バッテリー含む)は約612gで、EOS 60D(約755g)より約143g軽量化されています。
幅も13mm、高さは16mmほどR7の方が短く、一回りコンパクトです。一方でグリップは十分に張り出しており、手が大きめの人でも握りやすいデザインになっています。
実際、大型望遠レンズを装着してもホールド感は良好で、手持ち撮影で振り回しやすいバランスに仕上がっています。
ボディの剛性や造りも、ミドルクラスに相応しいしっかりしたものです。マグネシウム合金シャーシと防塵防滴構造を採用しており、雨天や砂埃の多い環境でも安心感があります。
この点はアウトドアやレース観戦での撮影が多い筆者にとって大きな利点です。
操作系は、従来の一眼レフから大きな変化が見られます。EOS 60Dでは本体上面にサブ液晶(肩液晶)を備えていましたが、R7ではサブ液晶が廃止され、その代わりに背面モニターや電子ビューファインダーで情報確認するスタイルに変わりました。背面にはマルチコントローラー(ジョイスティック)一体型のホイールドイヤルが新設計で配置され、主要ボタン類も右手側に集約されています。
初めは戸惑いましたが、慣れるとEVFを覗きながら親指で直感的にAFフレーム移動や設定変更ができ、スムーズに操作できます。これは動きものを追う撮影時に非常に便利です。
背面モニターは3.0型のバリアングル式LCDで、これは60Dと同じく自由な角度で開閉・回転が可能です。異なるのは解像度と機能で、R7のモニターは約162万ドットと高精細化し、さらにタッチパネル操作に対応しました。
ライブビュー時のタップでAFポイント移動やメニュー操作が直感的にでき、動画撮影やローアングル撮影でも快適です。一方、60Dに搭載されていた内蔵フラッシュはR7では非搭載となりました。ストロボが必要な場合はホットシューに外付けする必要がありますが、その分上部がスッキリしており、耐候性向上や堅牢性に寄与しているとも言えます。
Canon EOS R7の背面。右上にAF-ONボタンと一体化したホイール式のサブ電子ダイヤルが配置され、直感的な操作が可能。
電子ビューファインダー(EVF)は0.39型・約236万ドットのOLEDが搭載されています。
光学ファインダーのEOS 60D(視野率96%・倍率0.60倍)と比べると、R7のEVFは視野率100%・倍率0.72倍と見えの広さ自体は向上しています。
実際、ファインダーを覗いた瞬間に撮影前の露出やホワイトバランスのプレビューが確認できるのは、ミラーレスならではの便利さです。特に逆光や暗所での撮影で、仕上がりを確認しながら設定を追い込めるメリットは計り知れません。しかし解像度自体は最新フルサイズ機などと比べるとやや控えめで、明るさや精細感の点で「一眼レフの光学ファインダーほどの感動はない」というのが正直なところです
とはいえ、初めてEVFを使う60Dユーザーにとっては十分実用的で、撮影になじんでくれば違和感は薄れていくでしょう。
その他、細かな点ではデュアルSDカードスロットの採用も見逃せません。
R7は高速UHS-II対応のSDカードを2枚同時に使用でき、RAW+JPEGの分割記録やバックアップが可能です。一方60DはSDカードスロット1基のみでしたので、信頼性・利便性が向上しました。
また、バッテリーはR7がLP-E6NH、60Dは旧型のLP-E6ですが形状は共通しており、手持ちの60D用バッテリーも流用可能でした※。
ただし公称の撮影可能枚数は60Dが約1100枚、R7は約660枚(LCD使用時)と大きく異なり、ミラーレス化による消費電力増加は実感します。長時間の撮影や旅行では予備バッテリーの携行が必須と言えるでしょう。
※R7ではLP-E6NH使用が推奨されていますが、筆者の環境では60D付属のLP-E6でも使用・充電が可能でした。ただし容量が劣るため撮影枚数はやや少なくなります。
EOS R7の画質とセンサー性能
EOS R7に搭載された約32.5メガピクセルのAPS-C CMOSセンサーは、従来のEOS 90DやM6 Mark IIと同等の高画素ですが、新開発のセンサーとされています。一方、EOS 60Dは約1800万画素でしたから、その差は実に1500万画素以上。
この高解像度化によって、撮影後のトリミング耐性は飛躍的に向上しました。実際、モータースポーツ撮影で遠くの被写体を大きく切り出したい場合でも、60Dでは画像が粗く限界がありましたが、R7では32MPの豊富な情報量のおかげで十分なシャープさを保ったままトリミングできます。
高画素化に伴うノイズ増加を心配していましたが、R7の高感度画質はむしろ60Dより良好に感じます。最新の映像エンジンDIGIC Xのノイズ低減処理やセンサー技術の進歩により、ISO感度は常用ISO32000まで拡張され(60Dは常用ISO6400)、実際の撮影でもISO3200程度までほとんど破綻のない画質です。
ディテールの劣化が目立ってくるのはISO6400~12800あたりからですが、必要に応じて躊躇なく使える範囲内と言えます。60DではISO1600ですでにノイズが気になっていたことを考えると、大幅な進歩です。
ダイナミックレンジに関しても、R7はRAW現像でシャドウを大きく持ち上げても粘り強く階調が残っており、暗部耐性が向上している印象です。逆光下でも白飛び黒つぶれを抑えた撮影がしやすくなりました。総じて、32.5MPという高画素ながらAPS-C機としてバランスの取れた画質であり、「キヤノンAPS-C EOS史上最高の解像性能」という謳い文句もうなずけます。
さらに見逃せないのはボディ内手ブレ補正(IBIS)の効果です。EOS R7はセンサーシフト式の5軸手ブレ補正機構を内蔵し、最大7.0段分の補正効果があります。
これにより、従来は手ブレが心配で使いづらかったスローシャッターにも果敢に挑めるようになりました。実際、夜景撮影で1/8秒程度までなら、三脚なしでもかなりの確率でブレずに撮影できています。キヤノンの一眼レフでは中級機までボディ内補正が無かったため、レンズ側のIS頼みでしたが、R7ではすべてのレンズが手ブレ補正付きになった感覚です。
これはEFマウントの古い単焦点レンズなどを流用する際にも大きな恩恵となります。

総合的に見て、EOS R7の画質はAPS-C機としてトップクラスであり、60Dから乗り換えることで画質面でも確実にアドバンテージを得られます。高精細なセンサーと強力な手ブレ補正のおかげで、撮影シーンの幅が広がりました。例えば風景の隅々まで写し取りたい場合や、室内や夕景での手持ち撮影など、60D時代には難しかった表現が可能(雑にとっても絵になる)になっています。
EOS R7のAF性能の進化
EOS R7で最も感動したポイントの一つがオートフォーカス性能です。デュアルピクセルCMOS AF IIによるセンサー全面の測距に対応し、その測距点は651点にも上ります(自動選択時は画面ほぼ100%をカバー)。これは中央9点(うちクロス9点)のみだったEOS 60Dとは次元の違うカバー範囲です。加えて、被写体検出・追尾機能の賢さにも驚かされます。EOS R7は上位機R3ゆずりの被写体認識アルゴリズムを搭載し、人間の瞳・顔・頭部はもちろん、犬や猫、鳥など動物の目や体、さらには自動車やバイクといったモータースポーツ被写体まで検出して追尾可能です。
まさに「カメラが被写体を識別して狙ってくれる」時代になったと実感しました。
実際、走り回る子供や素早く動くペットを撮影してみると、EOS R7はファインダー内で被写体に張り付くようにフォーカス枠が追従し、シャッターを切るとピントの合った写真が高い確率で得られます。EOS 60Dでは中央一点AFで追いかけながら連写してもピンぼけ写真が量産されがちでしたが、R7では瞳AFやサーボAFのおかげで「ジャスピンの決定的瞬間」が捉えやすくなりました。特に瞳AFはポートレートで威力を発揮し、人物の目に確実にピントを合わせてくれるので、開放F1.8の浅い被写界深度でもピント外しが大幅に減りました。
低照度下でのAFも強化されています。公式スペックではEV-5相当(ワンショットAF時)の暗所でもピント合わせ可能とされ、実際、薄暗い室内でもスッと迷いなく合焦してくれます。
60D時代は暗所やコントラストの低い被写体ではAFが迷いがちで、MFに切り替える場面もありましたが、R7ではそうしたストレスがほぼありません。
筆者が手持ちのEFレンズ(例えばEF-S 55-250mm IS STMやEF50mm F1.8 STM)をマウントアダプター経由で試した限りでも、AF駆動は60Dに装着した時よりも明らかに高速かつ正確でした。これはミラーを介さないオンセンサーAFによる効果で、像面位相差の精度の高さや、最新ボディ側の演算処理能力がレンズをより俊敏に動かしているのだと思います。要するに、「今まで使っていたレンズが見違えるような性能を発揮する」感覚です。60Dでフォーカスが遅く感じていたレンズでも、R7では機敏に被写体を追従してくれる様子に、思わず笑みがこぼれました。一方でAFの動作音は目立つため、実害はありませんが気になるようになったもの事実です。
なお、AF関連の操作について補足すると、R7では前述のマルチコントローラー付きホイールでフォーカスポイントの移動が直感的に行えます。加えて、タッチ操作でのフォーカス位置指定や、縦位置時にAF枠の移動範囲を限定する設定など、カスタマイズ性も豊富です。EOS 60DではAFエリアモードも限定的(スポット/シングルポイント/ゾーン程度)でしたが、R7ではケース別のサーボAF特性調整や被写体検出のオンオフまで細かく設定可能で、用途に応じて最適化できる点も好印象です。
EOS R7の高速連写と動体撮影性能
AF性能と並んで、動きもの撮影で威力を発揮するのが高速連写性能です。EOS R7はメカシャッターでも最高毎秒15コマ、電子シャッターでは毎秒30コマの連続撮影が可能です。
これは60Dの約5コマ/秒と比べて実に3倍~6倍もの速度アップになります。
実際に電子シャッター30コマ/秒を初めて試した時、そのシャッター音の無さとコマ送りの滑らかさに衝撃を受けました。まさに動画から切り出したかのような細かなコマが記録され、肉眼では捉えきれない一瞬の表情や決定的瞬間を逃しません。
例えばサーキットを走るレーシングカーの撮影では、60D時代は連写速度が遅く動きに追従しきれず、「ここぞ」という瞬間にシャッタータイミングを神経質に図っていました。R7では迷わず高速連写に任せてしまえば、一連の動きをコマごと記録でき、その中からベストショットを選ぶことができます。
筆者の体感では、歩留まり(ピントの合った決定的瞬間の撮影成功率)は60Dの頃より飛躍的に向上しました。キヤノン曰く「連写性能はもはやプロ機に迫るレベル」で、フラッグシップ機1D X Mark III(16コマ/秒)に僅差の性能とまで評されています。まさにAPS-Cの価格帯で1桁機の域に達した印象です。
連写時のバッファ(連続撮影可能枚数)も十分確保されています。筆者の使用するUHS-II V90カードでは、電子シャッター30fps・RAW記録で約3秒強(100枚程度)は連写可能でした。
JPEG撮影であれば400枚以上撮り続けても減速しないほどの大容量バッファです。60DはRAWで約16枚程度連写するとバッファフルに達していたことを考えると、雲泥の差があります。ただし30コマ/秒という超高速連写はデータ量も莫大になるため、連写後の書き込み待ち時間は多少発生します。そのためモータースポーツなどで要所要所のシーンを狙う際は、必要以上にシャッターを押しっぱなしにせずコントロールすることも大切です。
電子シャッターにはローリングシャッター歪みのリスクもありますが、R7はミラーが無いため振動もなく、電子先幕も併用できるため、通常の使用ではシャッターショックは皆無と言えます。また電子音で疑似シャッター音を出す設定も可能なので、静音性とフィードバックを両立できます。静かな室内や赤ちゃん・ペット撮影、コンサート会場などで無音撮影できるメリットは大きいです。
総じて、EOS R7の高速連写と動体追従性能は、60Dを使っていた頃からすると「別次元の世界」でした。これだけの性能があれば、野鳥や航空機撮影、スポーツ撮影などプロ顔負けのジャンルにも本格的に挑戦できるポテンシャルがあります。趣味で動体撮影を楽しむユーザーにとって、R7は価格以上の価値を感じさせてくれるでしょう。
EOS R7のレンズとマウント互換性
EOS R7はRFマウントを採用しています。RFマウントはフルサイズミラーレス用として2018年に登場した新世代マウントで、内径54mm・フランジバック20mmという特長を持ち、高性能なRFレンズ群が展開されています。
R7はそのRFマウントを流用しつつ、APS-Cサイズのイメージサークルに最適化されたRF-Sレンズにも対応する形です。現在(2025年時点)RF-Sレンズはまだ種類が少ないものの、発売時の標準ズーム「RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM」やパンケーキ的広角ズーム「RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM」が用意されています。筆者もR7購入時に18-150mmのレンズキットを選びましたが、このレンズ1本でフルサイズ換算29mm相当の広角から240mm相当の望遠までカバーでき、旅行や散歩撮影で重宝しています。描写もキットレンズとしては良好で、特に中望遠域で背景ボケを活かしたポートレートもこなせました。
また、同時に購入した単焦点レンズ「RF35mm F1.8 MACRO IS STM」はR7との相性が抜群でした。開放F1.8という明るさで室内や夜景でもシャッタースピードを稼げる上、0.5倍まで寄れるハーフマクロ性能も持ち合わせています。APS-C機に35mmを付けると約56mm相当の画角になり、人間の見た目に近い自然なスナップ撮影が楽しめます。実際、R7+RF35mmで撮影した家族の何気ない一コマは、背景が柔らかくボケて被写体が浮き上がり、60D+標準ズームでは得られなかった印象的な描写が得られました。明るい単焦点レンズで表現の幅が広がるのも、R7に高感度性能と手ブレ補正が加わったことで一層活きていると感じます。
では、手持ちのEFレンズ資産はどうなってしまうのか? ここは多くのEOSユーザーが気になる点でしょう。結論から言えば、「EFおよびEF-Sレンズはマウントアダプター経由で問題なく使用可能」です。
筆者もキヤノン純正のマウントアダプター(EF-EOS R)を介して、EF-S 55-250mmやEF50mm F1.8 STM、さらにはEF24-105mm F4L IS USMなどを試しましたが、オートフォーカス・露出ともに100%近い互換性で動作しました。描写に関しても、R7の高解像度センサーのおかげでレンズの性能を余すところなく引き出せている印象です。特に驚いたのは、EF-S 55-250mmのAFスピードが60D使用時より向上したことです(前述の通り)。
加えてボディ内手ブレ補正が効くため、非ISのEFレンズでも安定して撮影できました。アダプター装着によるデメリットは物理的に全長が少し伸びる程度で、重量バランスも大きく崩れることはありません。迷彩柄のシリコンカバーを装着したR7に望遠レンズ+アダプターの組み合わせでも、見た目の一体感は保たれています。

RFマウントのネイティブレンズが現状少ないとはいえ、EFマウントの豊富なレンズ資産がそのまま使えるのは大きな強みです。実際、60DユーザーがR7へ移行するハードルは非常に低いと感じました。使い慣れたお気に入りのレンズを引き続き活用できるうえに、将来的に魅力的なRFレンズが登場すればそれも選択肢に入れられます。現在、サードパーティー製のRFマウントレンズが少ない点はデメリットですが、キヤノン純正で今後RF-Sの超広角や高倍率ズームなどが拡充されてくることに期待したいです。
最後に、筆者なりのレンズ構成の楽しみについて触れておきます。今回R7と同時に揃えた18-150mmズームと35mm単焦点の組み合わせは、実に使い勝手が良くコストパフォーマンスに優れたセットでした。旅行や子供の行事ではズーム一本でオールラウンドに対応しつつ、ポートレートやテーブルフォトでは単焦点に付け替えて明るい描写を楽しむ、といった使い分けができます。ズームで構図の自由度を確保しつつ、単焦点で表現力を追求できるこの組み合わせは、写真の幅を広げたい初心者・中級者に特にお勧めできます。60D時代から使っているEF50mm F1.8(撒き餌レンズ)もR7で引き続き現役ですので、予算に応じて手持ちレンズを活かしつつ、新しいRFレンズに手を出してみるのも良いでしょう。
EOS 60Dからの主な進化ポイント
以上、各項目ごとに詳しく見てきましたが、ここで改めてEOS 60DからEOS R7への主な進化点を整理してみます。
- 有効画素数アップ:18MP(60D)から32.5MP(R7)へ大幅向上。より大きなプリントや大胆なトリミングが可能。
- AF性能:測距点9点→651エリアに拡大。瞳AF・被写体追尾(人物・動物・車/バイク)対応で、動体への食いつきが飛躍的に向上。
- 連写速度:約5コマ/秒→最高30コマ/秒に大幅高速化。プロ機並みの連写性能で、決定的瞬間を逃さない。
- 手ブレ補正:ボディ内手ブレ補正新搭載(最大7.0段)。60Dは非搭載だったため、あらゆるレンズで手ブレ軽減が可能に。
- ファインダー:光学OVF(60D)→電子EVF(R7)へ。視野率96→100%、倍率0.60→0.72倍。露出プレビュー可能だが、解像度や表示の滑らかさは光学式とは異なる。
- 動画性能:フルHD(1080/30p)まで→4K/60p対応(7Kオーバーサンプリング4K/30pも可)。10bitログ撮影対応など動画機能も強化。
- 記録メディア:SDシングルスロット→UHS-II対応デュアルスロット。バックアップや振り分け記録が可能に。
- 通信機能:Wi-Fi/Bluetooth搭載でスマホ転送やリモート撮影が容易に(60Dは非搭載)。
- バッテリー駆動時間:CIPA約1100枚→660枚と短縮。ミラーレス化によるものだが、USB充電対応でモバイルバッテリーから給電可能。
- その他操作面:内蔵フラッシュ廃止、トップ液晶廃止、ジョイスティック新設計などデザイン刷新。防塵防滴も継承。
こうして並べると、R7は60Dから本当に多くの点で進化していることが分かります。とりわけAF・連写・手ブレ補正といった機動力に直結する部分での進歩は、スペック上のみならず実撮影においても体感できるレベルでした。
EOS R7の良いところ
実際にEOS R7を使ってみて「これは良い!」と感じたポイントを改めてまとめます。
- 抜群の高速連写とAF追従性能: 15コマ/秒メカ連写&30コマ/秒電子連写と、全域・被写体検出対応AFの組み合わせにより、動く被写体でも高い歩留まりで撮影可能。子供やペット、スポーツ被写体の撮影が格段に容易になった。
- 高解像でシャープな画質: 32.5MPの高画素センサーがもたらす精細な描写。クロップ耐性が高く、大判プリントやトリミング前提の撮影でも安心。高感度画質もAPS-C機として優秀で、暗所性能が向上。
- ボディ内手ブレ補正の恩恵: センサーシフト式IBISが最大7段分の補正効果を発揮し、手持ち撮影の自由度がアップ。非手ブレ補正レンズでもスローシャッターが使え、動画撮影時の安定性も向上。
- レンズ資産を活かせる互換性: RFマウント採用ながらEF/EF-Sレンズをマウントアダプター経由でそのまま使用可能。手持ちのレンズを引き継げるため、移行コストを抑えつつ段階的にRFレンズシステムへ移行できる。
- 洗練された操作性と堅牢性: 小型軽量ながら深いグリップと理想的なボタン配置でホールド性と操作性が良好。防塵防滴ボディでタフな環境にも対応し、アウトドアでも安心して使える。
- デュアルカードスロットと豊富な機能: ダブルスロットによるバックアップ記録や、USB充電・給電対応、電子水準器搭載、自動水平補正機能など、現代的で便利な機能を多数搭載。撮影後のスマホ転送もWi-Fi経由でスムーズ。
EOS R7の気になるところ
一方で、EOS R7を使う中で感じた注意点や惜しいポイントも挙げておきます。
- バッテリー持続時間の短さ: EVFや高速プロセッサーの影響でバッテリー消費が多く、CIPA基準で約660枚と60Dの半分程度。予備バッテリーは必携で、長時間の撮影時はこまめな充電やモバイルバッテリーからの給電が必要。また、アプリ連携によりスマホにデータを移していると、消費電力も上がり、稼働時間が低下します。
- 内蔵フラッシュ非搭載: スピードライトを使う本格派には問題ないが、ちょっとしたスナップで内蔵フラッシュを使っていた人には残念な点。外付けフラッシュを持ち歩かないと暗所での簡易撮影ができない。
- RFレンズラインナップと価格: RF-Sレンズの種類がまだ少なく、広角端や大口径レンズの選択肢が限られる(現時点で純正超広角ズームが無い等)。RFフルサイズ用レンズは高価なものが多く、サードパーティ製も制限があるため、システム拡充にはコストがかかる。
- EVFの見え: 解像度や発色は良好なものの、最新高級機や光学ファインダーと比べると見劣りする部分も。特に60Dなど光学ファインダーに慣れたユーザーだと、EVFの輝度や遅延に最初は違和感を覚える可能性がある。態勢が崩れているときやファインダーから離れているときに端がぼやけて見えるのも気になります。
- 高連写時の注意: 30コマ/秒の電子シャッター連写は便利だが、RAWではバッファが数秒で一杯になるため、長秒連写には限界がある。また電子シャッター使用時は被写体によってローリングシャッター歪みが発生する場合があるので、動きの速い被写体ではメカシャッター(15コマ/秒)に切り替えるなどの工夫が必要。
- 操作レイアウトの好み: 背面ホイールドイヤルとジョイスティックの一体構造はユニークだが、人によっては誤操作や回しづらさを感じる場合もある(筆者も初めは露出補正値を行き過ぎてしまうことがあった)。慣れで解決する部分ではあるが、従来の十字キー+ホイールに慣れた方は最初戸惑うかもしれない。電源ボタンが右に寄ったのも最初は慣れませんでした。
まとめ
EOS R7は、旧世代のEOS 60Dユーザーにとって「すべてがワンランク上に進化した」理想的なアップグレード機です。高画質な32.5MPセンサーと強力な手ブレ補正、圧倒的に賢くなったAF、そしてプロ機に迫る高速連写――これら全てを備えつつ、扱いやすいサイズと価格帯に収まっている点が驚異的です。実際に使い込んで感じたのは、「写真撮影がこれほど快適で楽しくなるのか」ということでした。
60Dでは撮れなかった瞬間が撮れるようになり、歩留まりが上がったことで撮影そのものに集中できるようになりました。特に子どもの成長記録やペットの仕草、サーキットを疾走する車・バイクの姿など、これまで以上に「撮りたい瞬間」を逃さず残せる安心感があります。また、R7を手にしてから写真表現の幅も広がり、新しいレンズにチャレンジしたり、夜景や動画撮影にも挑んでみようという意欲が湧いてきました。
もちろん完璧なカメラではなく、バッテリーの持ちやレンズシステムの成熟度など課題もありますが、それを踏まえてもなおR7の魅力は光ります。ミドルクラスの価格でここまで多才なカメラを手に入れられる時代になったことに、カメラ好きとして嬉しさを感じずにはいられません。EOS 60Dから乗り換えを検討している方は、ぜひ一度R7を手に取ってその進化を実感してみてください。きっと、ファインダー越しに広がる新しい世界にワクワクするはずです。
筆者自身、このEOS R7を相棒に、これからも子どもとのお出かけ写真やブログ用の撮影を存分に楽しんでいきたいと思います。次回の記事では、実際の作例を交えつつEOS R7のさらなる魅力や細かな使い勝手について紹介する予定です。

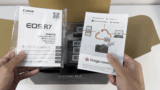
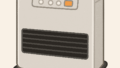

コメント