2019年4月から2024年2月まで、私は東京都内にある精神科救急病棟で勤務していました。そこは、365日年中無休で入院患者を受け入れる病棟。私が所属していたのは女性患者専門の病棟で、毎日が緊張感に包まれていました。
受け入れる患者さんは、統合失調症、うつ病や躁うつ病といった気分障害、パーソナリティ障害、摂食障害、アルコールや薬物などの依存症、さらには認知症まで、本当に多様でした。年齢層も幅広く、10代から高齢の方までさまざまです。
こうした環境の中で常に悩まされるのが、「患者さんとのかかわり方」でした。病状や背景によって求められる対応はまったく違い、同じように接してもうまくいかないことも多くありました。
行動制限という現実
精神科救急病棟では、ときに自傷や他害につながる行動が見られることがあります。そんなとき、患者さん自身や周囲の安全を守るために、やむを得ず「身体拘束」や「隔離」といった行動制限を行わざるを得ません。
もちろん、それは決して望んで行うものではありません。薬物療法と並行しつつ、できるだけ早く安全を取り戻せるように努めました。そして医師の診察で「自分の安全を守れる」と判断されると、制限は解除され、病棟内で他の患者さんと共に治療を続けていきます。
印象に残った患者さん
① 30代女性・パーソナリティ障害
忘れられない患者さんの一人に、30代の女性がいます。彼女はパーソナリティ障害を抱え、幼少期から実親による虐待を受けてきた背景がありました。その影響もあって、仕事や人間関係、そして家庭生活のすべてにおいて困難を抱え、常に不安定な状態にありました。
入院当初は、感情の起伏が激しく、少しの出来事で強い怒りや不安を表すことがありました。時には、周囲の人や物に対して攻撃的な行動をとってしまうこともあり、スタッフとしても緊張感を持って対応しなければなりませんでした。
それでも、日々関わっていく中で見えてきたのは、彼女の「心の奥底にある寂しさ」でした。信頼してきた人から裏切られる経験を繰り返してきた彼女にとって、安心できる人間関係を築くことはとても難しいことでした。彼女には夫と子ども(未就学児)1人がおり、彼女は一人の母親として、一人の女性として自分の在り方を入院中もずっと葛藤を繰り返していました。退院後、彼女は家族をのこして自殺したと、彼女と仲の良かった患者から聞いて驚きました。
どんなときであれ、私たちスタッフが「あなたを受け止めていますよ」という姿勢を示すことが重要でした。小さなことですが、話を遮らずに最後まで聞く、怒りをぶつけられても冷静に対応する、良い行動をしたときにはしっかり言葉で伝える――そんな積み重ねが、少しずつ彼女の表情を変えていきました。
② 10代女性・統合失調症
10代で統合失調症を発症した女性のことも強く記憶に残っています。彼女は専門学校に入学した頃から突然、幻聴や妄想に悩まされ、混乱して暴れる状態で入院しました。
症状が強い時期には、衣類を首に巻きつける、水を大量に飲むなど、自傷につながる行動も繰り返されました。行動制限や薬物療法を経て症状が落ち着いた頃には、「あれは妄想や幻聴の影響だった」と自ら振り返ることができるほど回復していました。
退院を目指して病院の周囲を一人で散歩することも許可され、毎日「いってきます」と笑顔で病棟を出ていく姿が日常になっていました。
しかしある日、その「いってきます」が最後となりました。昼頃、消防から「高いビルから飛び降り、心肺停止状態で搬送された」との連絡が入り、そのまま彼女は帰らぬ人となったのです。
この出来事は、私に大きな衝撃を与えました。どんなに安定して見えても、患者さんの心の奥底には計り知れない苦しみが潜んでいる。そのことを痛感し、日々の小さな変化に敏感であること、傾聴と観察を怠らないことの大切さを強く学びました。
毎日が葛藤の連続
この5年間は、正直なところ葛藤の連続でした。
「どうすれば患者さんに寄り添えるのか」
「安全と自由をどう両立させるのか」
その答えは簡単には見つかりませんでしたが、ひとつ確かなのは、患者さんが少しずつ落ち着きを取り戻し、病棟で笑顔を見せてくれる瞬間が、何よりも大きな喜びだったということです。
精神科救急病棟での勤務は、決して楽ではありませんでした。ですが、あの現場で学んだことは今でも私の財産になっています。患者さんの命と生活に直結する現場に立ち続けた経験は、これからも忘れることはないでしょう。



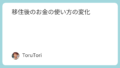
コメント